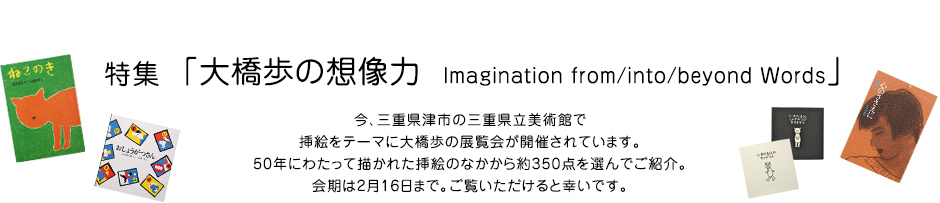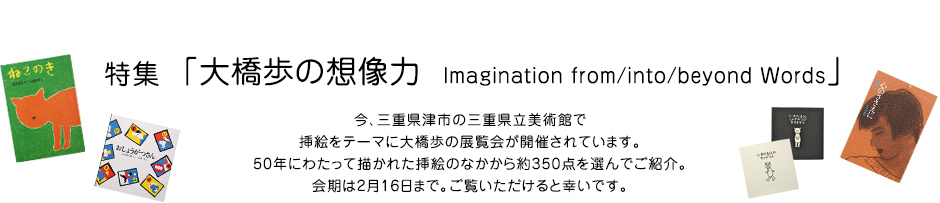三重県立美術館で展覧会がスタートしてちょうど1週間になる1月11日、詩人の長田弘さんをお迎えしてのアーティスト・トークが開催されました。
絵本『ねこのき』や詩集『深呼吸の必要』、エッセー『風のある生活』などで本の装丁や挿絵の仕事をさせていただいているけれど、今まで一度もお会いせずにきた尊敬する詩人との対談に、大橋は2013年のうちから緊張していました。でも、はじまってみたらぜんぜん大丈夫だったのでした。ふだんの言葉をつなげ、ときおりユーモアを交えながら遠く深く広がっていく長田さんの世界に引き込まれ、気がつけば予定時間をオーバー。長田さんとの対話の中で、大橋が不思議に思っていたことやずっと抱いていた不安や疑問がすうっと溶けていくように思えた瞬間もありました。
当日は多くの方がおいでくださったにもかかわらず、会場の都合で聞いていただけなかった方もいらっしゃいました。おわび申し上げるとともに、貴重なお話の一部ではありますが、ここで紹介いたしますのでぜひお読みいただければと思います。

三重県立美術館の講堂で150名の方に参加していただいたアーティスト・トーク。東京や岐阜など遠くから来ていただいた方も多くいらっしゃいました。

詩人の長田弘さんは1939年福島市生まれ。1965年『われら新鮮な旅人』(みすず書房)でデビュー。代表作に『私の二十世紀書店』『深呼吸の必要』『記憶のつくり方』『世界はうつくしいと』『詩の樹の下で』など。
「いろいろな感じ方をするのが楽しい」
長田さんと大橋の対談は、長田さんの詩集『奇跡ーミラクルー』(2003年、みすず書房)のことからはじまりました。この詩集は季刊誌『住む。』に連載なさっていた詩を中心に構成されているのですが、大橋は不思議に思っていたことがあったのです。
連載中に雑誌で読むのと、本になってから読むのと、新聞に取り上げられているのを読むのとでは違って思えるのです。それを長田さんは『ほんとうのあり方ではないか』とおっしゃいます。
「詩だけでなく絵もそうですが、書いてあることは同じでも、それをどこで見たか、いつ読んだか、どんな時に読んだかによって違ってみえるというのがほんとうのあり方じゃないでしょうか。絶対これじゃないといけないというのでも、こう受け取ってもらいたいということでもなく。
いろんなことを言ったり考えたりするときに、最初に原因があって結論があるようにみんな思っているけれど実際はそうではなくて、最初に結果があってそれからそう思っているのはどうしてだろうと考えると、原因は時と場所、TPOによって全然違ってくるとわたしは思っています。大橋さんの絵も展覧会で見るのと、雑誌に出た時と、雑誌を懐古的に見る場合とみんな違うと思うんです。その違いを楽しめるのがいちばんいいんじゃないでしょうか」。
「大橋さんの絵の見え方が変わりました」
長田さんは今日大橋に会ったことで絵の見方が変わったともおっしゃいます。
「作品とか作者には “ 振る舞い、behavior “ というのがあるんですね。こうして座っているとわからないけれど、今日来て初めて会って一番感じたことは大橋さんて足が速い(笑)。とっとことっとこって歩くんですよ。いやもうわーっと思ってそれについていくのがたいへんで。今まで作品を見ていて足の速い人という印象がなかったけれど、これからはそれが残っていく。そういうものが絵の見方を少し変えてくれるからおもしろいです」。

対談が始まる前に、展覧会をごらんいただきました。長田さん、このときひとつ気になっていたことがありましたがーそれはのちほど対談で明かされることに!
「詩も絵も一緒に成長していく」
長田さんによれば、『本はできた時に終わりではない』のです。
「書くことは書き終わったら終わりだし、絵も描いた時点で終わり。そこまで長い時間がかかっています。でもそこからこんどは、読むこと、見ることがはじまる。読む人、見る人といっしょに、それからずっとその本が、作品が育っていく。そうやって出来あがってからゆっくり完成していくというのも、本や作品にはあるんですね」。
「自分の描いた挿絵が長田さんのお話にあっていたのか、長田さんに大丈夫と思っていただけたか」大橋はずっと不安でいました。でも、長田さんは詩も、詩の後を追いかけて描かれる絵も、本となって読まれて一緒に成長して行くとおっしゃる。それはつくり手としては嬉しいと同時にとても重みのあることのように感じました。

今年の元旦に毎日芸術賞を受賞した『奇跡ーミラクルー』(2013年 みすず書房)。カバーの絵はイタリアのルネッサンスの画家、ロッソ・フィオレンティーノの『リュートを弾く小さな天使』。「絵で音楽を描いている。音がしないのに聴こえるようなのが好きでカバーにさせてもらったんです」と長田さん。

長田さんの詩集から。「おなかがすくし、台所に入ろうという気持ちになる」と大橋が大好きな『食卓一期一会』(1987年 晶文社)と大橋が挿絵を描かせていただいた『深呼吸の必要』(1984年 晶文社)。ともにブックデザインは平野甲賀さん。文字はブルーやグリーン。紙の余白を生かした本づくりも印象的です。

長田さんの絵本『ねこのき』のねこは今回の展覧会のメインキャラクターのような存在。美術館の入り口でお客様を迎えてくれていますが、たしかにひげがありません!これはたいへん?
「自分の書くものを通して時代が立ち現れる」
大橋はかつて自分の仕事、イラストレーションは印刷されることを前提にしているものであるとして、額に入れて展示されることを拒絶していたことがありました。その頃からはずいぶん時間が経ち、距離を置いて自分の絵をみることができるようにはなったけれど、こうして美術館で展示されているのをみるとどこかちょっと落ち着かない気持ちがあります。
でも、長田さんが大橋に本の挿絵を依頼した背景には、まさにその『額に入れることを拒絶していた』時代があったとおっしゃいます。
「大橋さんとわたしはほぼ歳が同じで、それぞれのジャンルはちがうけれど、1960年代という非常にユニークな、きわだった時代を共通に経験しています。1960年代は本、音楽、美術、デザイン、ファッション、それからいまにいたるまでの、日々のあり方というのが世界中でいっぺんに変わっていった時代で、ライフスタイルという新しいコンセプトが決定的になっていった時代でした。そういう中で過ごすと、自分は自分であるけれども、実は時代が大橋さんの描くものを通して立ち現れてくる、わたしも自分の書くものを通して時代が立ち現れてくるということに気づかされます。ライフスタイルというものがすっかり変わっていった時代、そしてそれが新しい大きな個性をつくっていった時代を、それぞれに、しかし同じに経験しているんですね」と長田さん。大橋も大きくうなずきます。
「対話ができる人と仕事をしたい」
「挿絵は書かれている言葉や文にそって絵をつけるものだと考えられがちだけれど、わたしは文と絵が対話をするのだと思っていて、会ったことはなくても、いっしょの場所にいるなあと思う人となら、対話としての仕事ができると確信しているんです。大橋さんにもお会いしたことはなかったけれど、ずっとお仕事を拝見してきて、そう思いました」
絵を依頼する人は自分で決めるという長田さん。絵本ができあがるまで会った人はこれまでひとりもおらず、相談したこともないけれど、この人だったらなんかやってくれるだろうという感覚は今まではずれたことがないとおっしゃいます。
「でもみなさんご存知でしょうか。『ねこのき』の猫にはひげがないんですよ」。
長田さんにそう言われて大橋はあわてました。『ねこのき』は1996年の作品ですが、今の今までひげがないことに気がついていなかったのです! この続きは対談の実況中継でお読み下さい。

長田さんと大橋は季刊誌『住む。』の巻頭連載を10年以上隣り合わせで続けている関係でもあるのですが、今日が初対面。大橋のつくっているカレンダーを毎年ずっと愛用してくださっているそうです。

今日の大橋はa.の襟なしワンピースの胸元に掛井五郎さんの大きなスプーンをつけてきました。長田さんの詩集『食卓一期一会』に少しでも敬意を表せたら、と思って。

長田さんは1960年代からずっとジーンズをはいています。「一度スーツなるものをつくってみたのですが、ベルトの位置があまりにも高くて着た気になれない。ジーンズは僕にとって生地ではなくベルトの位置(笑)。習慣は大事、習慣は文化だと思っています」
ねこのひげとしっぽの話
長田(以下敬称略)「不思議なことに見ている人のほとんどが気づかない。絵本を読んだ人に『ひげ、あった?』と聞くんですけれど覚えていないんです。ふつう猫はひげからはじまるようなものなのに、わたしも気がついたのは本ができあがって後になってからです。編集者も気がつかない。あれは単純な絵のように見えますけれど、すごいマジック。意図したんですか?」
大橋「いえ全然。今言われて思い出しました、すみません」
長田「今日の展覧会の絵の中に、猫がいっぱいるから見ましたが、他のはちゃんとひげがはえているんです。大橋さんは猫にひげはないと信じ込んで描いているのかなとも思っていたのですが」
大橋「いえ」
長田「その意味ではあの絵は世界的に貴重な絵です。世界で初めて、あれ一つです(笑)。意図してでなかったから真実になった。読んだ方が気づきもしないというのもすごいです」
大橋「お話があまりにも印象的で暖かく心に残ったのでひげどころではなかったのかもしれません」
長田さんは今猫といっしょに暮らしています。
長田「ねこにはとても不思議なところがあって、大橋さんが描いてくださった猫には尻尾があります。ところが日本の猫には、ヨーロッパの人が見たら信じられないと言いますが、“ごんぼねこ”という尻尾のない猫が多いんです。あってもなくてもいいものをいっぱい持っているのが猫で、だから猫の尻尾はクエスチョンマークをしているのだというのがわたしの説(笑)」。
大橋「長田さんの猫はしっぽが長いですよね」。
長田「しっぽのある猫が好きなんです。しっぽがないと猫のことがよくわからない。猫はけっこうしっぽで語っているんですね。だから人間にもあるといいかなあとも思うけれどちょっと変かなあとも思う(笑)。でもあってもなくてもいいものを持っている生き物はすごく珍しいという気がします。でもほんもののひげのない猫にはまだ会ったことがありません」
大橋「すみません」
長田「いえいえ、あれこそ大橋歩の想像力そのもの」
大橋「いやーどうしてなんでしょう。全然思いつきません」
長田「それがよかった。『ねこのき』は非常に不思議な絵本です」。

津の駅で長田さんをお見送りしたときの写真です。なんと、大橋のVサインがねこのひげのようになっています。
「室と所は何が違うのかなあ」
長田さんのお話は、ひとつの糸口から次の糸口へ終わらない詩のように連なっていきます。
たとえば大橋の好きな詩集『食卓一期一会』についての話は言葉と食べることや料理の結びつきに。長田さんが本づくりのときに大事にしている”余白“についての話は『、』『。』『?』『!』『ー』といった声に出せないものを表す言葉や、意味しないものが意味している今の時代の表現に、といったように。長田さんの言葉に対するまなざしはいつも柔らかくそして真剣。次のようなエピソードも披露してくれて、会場が笑いに包まれました。
「ここには近鉄に乗って来たんですけれど、電車の電光掲示板に『洗面室は何号車と何号車についています』と出て次いで英語で『rest room〜』と表示されました。なるほど洗面室は忠実だけれど日本ではふつう洗面所というなあ、珍しいいい方でなじまないなあ、室と所は何が違うのかなあ、とくだらないことを考えていたらあっという間に着いてしまいました(笑)」。
結論のための話や価値をおしつけるような話はいっさいなさらない2時間のアーティスト・トーク。その最後に、会場にいらしていた方からの『時代が大きく変わっていくなかで思うことは?』という質問に対して「(記憶や大事なことを)忘れないための手立て、方法を自分の周りにどのように作っていくかが重要だと思う」と答えられたのがぴりりと心に残りました。
取材:田中真理子